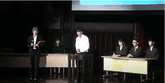
ある男は流行りの昆虫食ビジネスを立ち上げ、今勢いに乗っている起業家。
ところがある日、学生時代に起こした事件のことを当時の同級生にSNSで拡散されてしまう。
数ヶ月のうちに、彼の会社の売上は大幅に減少。愛娘は学校でいじめを受け、彼自身もインターネット上での誹謗中傷に苦しむように——。
とはいえ、彼が過去に事件を起こしたこともまた事実。時流に乗っている起業家に隠された黒い過去が周知されることは、取引先や消費者にとって一定の意味をもち、公共性・公益性があることかもしれません。
犯罪歴についてのSNS投稿は、プライバシー権の侵害に当たるのか。
それとも、公共性・公益性があるものとして、違法とされないか。
起業家の男は同級生とSNSプラットフォームの管理者を相手どって訴えを提起します。
果たしてどんな判決が下るのでしょうか——。
「プライバシー権」
みなさんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
各個人の守られるべきプライバシーは、我々の「知る権利」「表現の自由」と衝突します。
守られるべきプライバシーと明かされるべき公共性を持った情報とは、どこで線引きをすれば良いのでしょうか。SNSによるプライバシーの開示は、今を生きるみなさんにとって非常に身近な問題に感じられると思います。
今年度、五月祭にて東京大学法律相談所がお送りする第75回模擬裁判のテーマは「個人のプライバシーと公共性」です。
東京大学法律相談所とは、法学部の学生を中心に200名以上が所属し、今年で創立76周年を迎える歴史ある団体です。「医学部に附属病院があるように、法学部に法律相談所を」というコンセプトのもと、学問的研鑽と地域社会への貢献を理念に、無料の法律相談活動などを行っています。
模擬裁判は、今年で75回目を迎え、当相談所の創立以来続く伝統ある活動です。社会的関心の高い題材をテーマにした裁判劇を通じて、多くの方から遠い存在と思われがちな法律を身近に感じていただくことを目標としています。
本年度模擬裁判のテーマ・あらすじの概略
ここからは、本年度のテーマである「インターネット上のプライバシー侵害」と模擬裁判のあらすじについてご説明していきます。
昨今、SNS等のインターネット上の空間でのプライバシー侵害が社会的問題となっています。皆さんも、投稿者が巨額の賠償を請求されたという事案を、ニュースで見たことがあるかもしれません。
インターネットは、匿名で相手の顔を見ずに気軽に書き込める場所です。しかし、常にその内容は全世界に公開されており、知らず知らずのうちに他人の人生を狂わせる凶器にもなりえます。
今年度の事例では、大学時代に犯罪を犯した原告は、10年以上経ってから当時のサークル仲間によってブログ型のSNS「いろはブログ」で犯罪事実を暴露されました。
その後、原告自身の経営する会社が取引先の会社から取引中止を言い渡され、また、娘がいじめに遭い、不登校となりました。
これを受け、原告は経済的損害・精神的損害を受けたとして、投稿者を被告として損害賠償を求める訴えを提起しました。同時に、投稿の削除を要請されたにも関わらず、適切な対応をとらなかったとして、プラットフォーム「いろはブログ」の管理者に対しても原告は訴えを提起しています。
投稿一つで他人の人生、ひいてはその家族の人生までも変えてしまうことがお分かりいただけたでしょうか。誰でも気軽にSNS等で全世界に発信できる時代だからこそ、是非本年度の模擬裁判をご覧になっていただきたいです。
[広告]
テーマの法的問題について
では、今年度のテーマの法的な問題点を考えていきましょう。
原告が提起した訴えは、民法709条等によって「不法行為」に基づく損害賠償を請求するものです。
民法709条:
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
つまり、この裁判では全体を通して、被告である本件投稿の投稿者、プラットフォームの管理者が、原告に対して不法行為をしたといえるかどうかが争われています。
そして、複数の人が関与して不法行為を行うことを共同不法行為と言います。
投稿者、管理者による「共同不法行為」が認められるには、いくつかの要件が満たされていなければなりませんが、今回の訴訟で特に問題となっているのは、以下の3つの点です。
① 投稿者の行為が違法な権利侵害といえるか
② 原告の権利または利益が侵害されたことにつき、管理者に過失(≒不注意)が認められるか
③ 投稿者、管理者の行為と損害との間に因果関係があるか
まず①についてです。
判例は、他人のプライバシーを侵害する表現に対する損害賠償が認められるかを判断する際に、当該事実を公表されない被害者の利益(更生を妨げられない利益など)と加害者がそれを公表する理由(事実の社会的重要性、被害者の社会的地位や影響力、公表の目的など)とを比較し、前者が後者に優越するかを検討しています。
つまり、「被害者の利益 > 加害者が公表する理由(の価値)」といえるならば損害賠償が認められるというイメージです。
そして、投稿者が原告の過去の犯罪事実を公表する理由の大小を判断するため、投稿者の記事の通り2009年に原告は暴行をしたか(公表の真実性)、投稿者がブログに投稿した原告の過去の行為には公共性・公益性があるか(社会的重要性)、投稿者の投稿の目的は原告に対する嫌がらせなどではなかったのか(投稿の目的)という点が争われています。
次に②についてです。
共同不法行為の場面においても、行為者それぞれに民法709条に定められているような故意または過失が求められます。
民法709条(再掲):故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
原告と管理者との間では、管理者はブログ管理者としてどのような注意義務を負っていたかが問題となっています。
管理者が自身の注意義務を果たさなかったと認められると、原告がプライバシーを侵害されたことにつき、管理者に過失があったといえるということになります。
最後に③についてです。
原告と投稿者、管理者との間では、原告が被った取引の打ち切りによる経済的損害および娘のいじめ被害による精神的損害は投稿者、管理者の行為が原因であるかどうかも争点となっています。
直感的には、これらの損害が生じてしまったのは原告の過去が拡散されてしまったせいのように思えるかもしれません。
しかし、投稿者、管理者の側も複数の証拠を示してさまざまな反論を繰り出してきます。
模擬裁判をご覧になる際は、
①投稿者の投稿は違法といえるか
②管理者はブログ管理者として過失があったといえるか
③原告に生じた経済的・精神的損害は投稿者、管理者の行為に「よって」生じたものか
に注目されると、よりスムーズにお楽しみいただけると思います。
本年度模擬裁判の見どころ
裁判や法律と聞くと、劇の内容も難しく、堅苦しいものなのではないかと思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、心配はご無用です!模擬裁判は劇の冒頭で法律解説の機会を設けているため、その場で法律について学ぶことができます。また、模擬裁判は一つの本格的な演劇の舞台としても面白い内容になっているので、前提知識がなくてもあらゆる方に楽しんでご覧いただけます。
誰の言っていることが真実なのか?次々と繰り出される原告側・被告側双方からの鋭い尋問で、あなたが証人や原告・被告に抱く印象も目まぐるしく変化していくはずです。
現代を生きる私達にとって欠かせない存在となったインターネットですが、そのインターネット空間におけるプライバシーとはどうあるべきか?情報の公益性とは何なのか?観客の皆さまと共に考えられる裁判劇をお届けします。
そしてどんな結末を迎えるのか、演者も知らない緊迫の瞬間をぜひお見逃しなく!
また、法律にまつわるクイズや、法学部生との交流を通じて法律を身近に感じていただくための交流会も用意しています!お気軽にご参加ください!!
日時:2023年5月13日(土) 11:05~13:05(10:50開場)
場所:安田講堂
Twitterアカウント:@UT_mogisai2023
YouTube(リアルタイム配信を行います!):https://www.youtube.com/@user-yq7oi5xg9l













