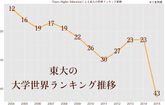
本稿は、瀧本ゼミ顧問の瀧本哲史氏と、そのゼミ生によるインタビューです。
第3弾:「革命抑止大学東大:革命、起こしませんか」と併せてお読み下さい。
- お名前:瀧本哲史さん
- 所属:東京大学法学部卒業
- 進路:学部卒業と同時に東大大学院法学政治学研究科助手に採用。助手の任期後、経営コンサルティング会社McKinsy&Companyで主に通信、エレクトロニクス業界の新規事業、投資プログラムのコンサルティングに従事する。その後、2000億円近くの債務を抱えていた日本交通の経営再建に取り組む。現在はエンジェル投資家として活躍する傍ら、京都大学で、起業論の授業を担当。東京・京都で、学生に対し企業分析と政策分析の自主ゼミ「瀧本ゼミ」を開く。
UmeeTは東大からすると「もったいないメディア」
ゼミ生: それでは始めようと思います。瀧本さんが学生メディアに出られるなんて意外ですね。
瀧本 : 私個人のブランディングに反するので、自分から出ようとは思いません。現状、大衆迎合的なPV稼ぎ記事もあるように見受けられますので…。何かメリットがないと、出ようとは思わないですね。なので、この記事は、「瀧本ゼミ」の記事広告みたいなものです。
僕自身の現状のUmeeTに対する認識は、恵まれた環境を活かしきれていない「もったいないメディア」といった所です。
ゼミ生: と、言いますと…
瀧本 : ある意味、東大広報室に「存在を許されているメディア」なんですよ。今のUmeeTは、東大広報室が目指すブランディングとはズレていますので。私立大学だと、学生がメディアに出ることを許可制にしていて、反すると処分する所もあります。
もし僕が編集部だったら、「東大自体、良い才能を集めているし、お金も沢山使わせてもらっているし、その分、学生自体も成果も出している」という実態を、きちんと世の中に喧伝するというブランド戦略をとりますね。
その方が、取材対象の東大生にとっても、記事を読んで刺激を受ける普通の東大生にとっても嬉しい訳です。受験生にしても「これなら東大に行ってみよう」というモチベーションになる。「心の闇が落ち着くので、こうであって欲しい」東大生像を面白おかしく流すような、娯楽TV番組とかを鵜呑みにしてる社会に対しても、実際の東大生はもっと多様で、東大がリーダーを輩出する機関として機能していることを喧伝できる。
UmeeTはある意味で、東大広報室にはできない、非公式な広報を自由に出来る存在な訳ですし、小回りがきいた取材だって出来る。目立たない才能を発掘することも出来る。マスメディアと違って、数十万、数百万人単位の人達の関心を引く必要もない。だから、PVをKPIにするのではなく、色々な分野の、本当のリーダーを取り上げて欲しい。
実際、ハーバードとかスタンフォードとかは、そうしているし、大学も学生もその責任を感じて、成果を上げようとしている。成果も出ている訳です。
瀧本 : もちろん、教育というのは歩留まりが悪いシステムなので、東大生全員がリーダーで尖った存在になれといっても難しい話かもしれない。そもそも東大生の定義は「東大入試を通って入学手続きをした人」です。しかし、入試の精度はそれほど高くないので、実際のところ、半分ぐらいの学生は「三回入試を繰り返せば、一回は合格できない」、その意味で「たまたま東大生」でしかない訳ですよ。だとすれば、2割ぐらいが卓越したことをすれば大成功ともいえる。
一方で、「たまたま東大生」であっても、大学時代になんかのキッカケで、尖ったことにチャレンジして卓越した実績を挙げるかもしれない、そう言う可能性もあると思うのです。
なので、せっかく東大のメディアをやるなら、その割合を最大化するきっかけを作るメディアにならないともったいなくないですか、ということです。こんな尖っている東大生がいるなら、自分もなにかやってみよう、そういう意欲を喚起するものであって欲しい訳です。 あるいは、メディアを通じて、多くの人が存在を知ることで、尖った人が世に出てもっとレバレッジを効かせられるようになるかもしれない。
[広告]
「とりあえず一番むずかしいから東大」
ゼミ生: 先ほどの「実績を挙げている東大生」を取り上げるべきだ、という話ですが、瀧本さんはいつもトップオブトップを見よと仰っています。
瀧本 : そうですね。東大生って、入学当初はちゃんと「話が違う!」って感じたはずなんですよ。東大に入るためにどれくらい努力をしたかは人によってかなり違いますけど、少なからずの努力をして入った大部分の学生たちは凄いガッカリ感がある。高校の延長どころか、高校以下の授業もあるし、別に東大でなくても良かったんじゃないかとか、東大にして失敗したと思う人も多いと思います。
でも、だんだん周りの雰囲気に絡め取られて、「社会人になる前に、大学生時代にしか出来ないことをしよう!」とか考えて、中途半端に遊ぶ人もいれば、途方に暮れてサークル・ジプシーになる人がいたりする訳です。
ゼミ生: かつての僕だ…
瀧本 : 安心してください、ほとんどの東大生はそうです(笑)。まだ、焦る2年生とかは偉い方です。普通の人間は、ダラダラと3年生になって、本郷でも学生生活を”こなし”、周りに自慢しやすいという点で会社を選び、まあこんなもんだろ、と思いながら卒業する。それどころか、その後の人生も「消化試合」のような人生になってしまう。
昔の週刊現代の特集の表現を使えば、「東大までの人」ってやつですね。
でもそれって、高校生の頃、思い描いてた東大生と違いますよね。
あなたの志はそんなもんでしたか?と。
ゼミ生: そこで、結果を出す東大生と、そうでない東大生の違いは何だと思われますか?
瀧本 : やっぱり、環境の効きが大きいと思います。東大って、そもそも主体性がない人間が「とりあえず一番むずかしいから文一」といった感じで入る大学、という面もある。そういった人間が何も考えずに学生生活を送ると、ダラダラ過ごしやすい環境にあります。私立中高一貫で、周りが皆東大、みたいな環境だと、言わずもがな。
そういった人間が直面しているのは、選択肢が多すぎて結局何も選べない、という行動経済学が言うような状況です。本当は機会自体はいくらでも転がっていて、サークル選びでも、進振りでも、気づいた時がチャンスな訳です。
ゼミ生: 具体的に言うと?
瀧本 : だからそういう態度がダメなんですよ(笑)。個人的な問題なんだから、個人的な解しか存在しません。ただ、「自分がこのままではダメだ」という危機感があるのなら、一念発起でフットワークを軽くして、環境を変えるために、説明会など広く見られてはいかがですか?ただ、一つ留意点があって、組織のリクルーティングにはエース級の人材しか露出しません。なので、組織の実態を知るためには、終了後のコンパでぼーっとしている学生とかに声をかけてみるといいと思います。
ゼミ生: それ、弊団体も返り血浴びるのでは…
瀧本 : だからFire制度があるじゃないですか。(編者注:瀧本ゼミでは、半期ごとに、発表の評価が基準に満たないなどゼミへの貢献が不足しているゼミ生が強制退会になる制度が存在し、全く油断できないシステムになっている。)
(次回へ続く)
第3弾:「革命抑止大学東大:革命、起こしませんか」と併せてお読み下さい。
なお、瀧本哲史氏が東大生を中心に開いているゼミ「東京瀧本ゼミ企業分析パート」は、2016年度5.5期生を募集しています。
詳細はこちら、ゼミ説明会の申し込みはこちらからご応募ください。





