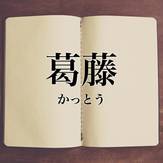※この記事は株式会社キタイエのPRです
「自分の過去を一つずつ紐解いていって、根本を知る。それがコーチングの役割の一つ」
……あなたの漠然とした悩みをスッキリと言語化する、コーチングの魔法を受けてみませんか?
コーチング? 魔法? この言葉に馴染みのないあなたも、この記事を読めばその意味がわかるはず。
今回は、日本最高峰のコーチングスクール「トランジション・コーチングスクール(TCS)」の代表を務めていらっしゃる喜多恒介さんにお話を伺い、コーチングとは何なのか、どういう魅力があるのかについてお聞きしました。
我々がインタビューをしていたはずが、いつの間にか取材陣がインタビューされていたり、今まで気づかなかったのが不思議な発見があったり。目から鱗のインタビュー内容を現場の雰囲気とともにお伝えします!
喜多さんは以前もUmeeTで取材させていただきました。タイトルがすごい……。
コーチングとの出会い、夢の中のカモメ
なぜ自分が大学生になったのかについて考える時の気持ちは、概ね、自分がカモメになった夢の気分と同じ。広い空と海を目の前に与えられ、自由に飛んでいいですよと言われた。大空には、一見すると自分そっくりなカモメが自由に飛び回っている。ふと目が覚めて、暗い寮の一室で初めに思うことは、「あれ、俺カモメだったじゃん。飛べばよかったのに。損したな……」
少し調べてみれば、同い年の学生達が色んなことを成し遂げているとわかる。彼らは行動力や熱意に満ちており、良い仲間を作って、色んなところからチャンスを勝ち取っている。それに対して、自分の手の内を見てみれば、自分の日常生活が空白のように思えてくる。授業に出て、レポートを書いて、テスト勉強をして、友達と話す。自分の中で何かが積み上がっていく感覚が全くないまま、一年が過ぎようとしている。
不思議なのは、時間がないわけでもなく、行動を起こそうとすれば起こせるはずなのに、自分が何もしないこと。自分の人生に自分で干渉することがこんなに難しいことだったのか、と驚くばかり。
自分の翼はどこへ行ったのか。レッドブルを飲んでもよくわからない。そんな時、一つの道を見つけてしまった。コーチングである。
学生証
- お名前:喜多恒介さん
- 経歴:東京大学農学部農業資源経済学専修卒
- 備考:農家と漁師の孫。教育系社会起業家として8年。最近、料理人も始めたとのこと。コーチングスクール「トランジション・コーチングスクール」を経営。
UmeeT取材陣
koi(筆者) なんか周りの人がみんなすごいなぁと思っている。
編集部 法学初心者。好奇心の赴くままに、気づけばサークル8個に所属していた。
[広告]
取材開始……の前に
筆者 なんだか、お話を聞くときの喜多さんの雰囲気は独特ですね。
喜多 そうかな。
筆者 柔らかい感じがして、初めて体験する雰囲気です。話を引き出す雰囲気や姿勢を意識されているのでしょうか。
喜多 吐くこと多めの呼吸をしていますね。やっぱり、初対面の人と話すときは、相手にリラックスしてほしいじゃない。プレゼンだってそうだよね。緊張している人のプレゼンを見ると、緊張しちゃうよね。だから、自分も落ち着けて、相手も落ち着けるような呼吸や姿勢を意識しているの。
筆者 なるほど。私も初対面だと緊張してしまう質なので、落ち着いた感じでお話しをしたいと思います。
こういうことなんだ、コーチングって
筆者 えっと、まずは、喜多さんの口から改めてコーチングについて説明していただけますか。
喜多 そんな事務的な話から始めちゃっていいのかな。もっと他に聞きたいことがあるでしょ?
筆者 あー、そうですね……。自分の中の悩みは、どうやって発見出来るのでしょう。何が悩みかわからない人も多いと思います。
喜多 どうしてそれを疑問に思ったの?
筆者 喜多さんがコーチングをされている動画を見たのですが、その中で、参加者が自分を縛っている価値観や悩みに自然と気づいていく過程を見て、魔法みたいだと思ったからです。
喜多 そうだね、サンプルとして、何か表面的な悩みはある?(編集部へ)
編集 自分が本当にやりたいことって何だろうという悩みですかね。色んなことに手を出しがちです。
喜多 超いいね。アクティブな東大生が抱えがちな悩みだね。でもこれは、表面上の悩み。理屈だけで考えれば、悩みではない。
筆者 どういうことでしょうか。
喜多 理論上は、全部チャレンジして、全部吟味して、自分のやりたいことをやっていけばいいじゃない。
編集 そうですね……それが出来たら苦労しませんよね……
喜多 そう、何で自分はそう思えないんだろう。それを考えてみよう。
喜多 まず、「だって」で言い訳してみて。
編集 「だって」ですか?
喜多 だって失敗が怖いんだもん、だって批判されたくないんだもん、だって普通のレールから外れるのが嫌なんだもん、みたいに。
編集 だって時間は有限なんだもん、ですかね。
喜多 でも、時間は70年あるわけじゃん。何で時間がないの?
編集 だって、人生設計の都合上、学生生活を続けられないからです。限られた大学生活の中にどれを選択してやっていくか。
喜多 大学って、僕は12年間行ったし、社会人になってから大学院に行ったり、休学したり、自由なんだけど。
編集 えーっと、出産をしたいので、そこを中心に考えたときに、職に就いて何年か経って安定した状態で出産を迎えたい。だから学生生活は早めに切り上げたい、です。
喜多 それだけが安定じゃないよね。フリーランスの方が安定するかもしれないし、旦那さん次第かもしれないし、実家にお世話になるのもありだし。
編集 まあ、そうですけど……
喜多 色んな選択肢がある中で、どうしてやりたいことを全て試さずに就職することを選んだの?
編集 自分の行きたい弁護士事務所は、新卒で直接入るのが一番良くある道だからです。
喜多 なんだけど?(笑う)
編集 そこを変えてまで、自分のやりたいことをやろうとは思っていない。
喜多 けど?
編集 えーっと、うーん……こういうことなんだ、コーチングって。
喜多 そうだよ。苦しいよ、だから。
編集 うーん。
喜多 今、対立が出てきたわけじゃん。やりたいことがあるけど、安定した人生設計を崩したくない。AかBかって感じじゃん。でも、本当はCなんだよ。コーチング的な観点で言うと。
喜多 君にはミッションがある。でも手段の選び方は色々。その中で「こうでなくてはならない」っていう縛りが君の中にある。思い込みがあって、でも実はこうしたかったんだという根っこを理解する。大切にしたい価値観や、それをもとにどういう行動をすればいいかに気づく。さっきの例だと、自分の「王道をいかなければいけない」という思い込みが外れたら、自分はもっとどういうことにチャレンジしていけるんだろうね。時間の制約とか、気になるかな?
[広告]
自分の本当にやりたいことって何だろう
編集 自分の本当にやりたいことは、どうしたら見出せるのでしょうか。
喜多 些細なことからだよ。例えば、好きなテレビや漫画から「私これずっとやってたじゃん」を見出す方法もあったりするよ。
編集 はぁ……
喜多 例えば、好きなYouTubeチャンネルはある?
編集 えーっと、東海オンエアです。
喜多 どこら辺が好き?
編集 考えたことないですね……。雰囲気とか、パフォーマンスとか……
喜多 他には?
編集 視聴者に媚びず、自分達が楽しいと思えるものを共有しているところですかね。
喜多 いいね。他は?
編集 ……発想力、飽きさせない企画力ですかね。
喜多 もっと教えて。
編集 メンバー個人の魅力があるところです。
喜多 それって、普段やっていること、UmeeTでの活動にどう繋がってる?
編集 そうですね……、UmeeTに入ったきっかけはネタ記事を書きたいという気持ちでした。例えば、クリスマスに一晩でイルミネーションいくつ回れるか、千円でクリスマスデートしてみたとか、ふざけた記事をまあ、多分YouTubeと同じような感覚で高校時代に読んでいました。それを自分も書きたいなと思うし、文章で読者を楽しませたい。自分が感じたネタ記事の良さを読者に伝えたい。
喜多 もし、両親も周りの人も弁護士にならなくていいよって言って、好きな職業につけるって言われて、しかもその才能があって、弁護士と同じくらい稼げるってなったら、どんな職業に就きたい?YouTuberもいいし、放送作家とかでもいい。一つじゃなくていいよ。
編集 うーん、それでも弁護士になるんだと思います。親やお金という観点は確かに職業選択に影響していないことはないけど、一番大きな要因は、社会の役に立つ王道の仕事に就きたいという気持ちです。
喜多 自分のやる職業が、実はもう次の時代の王道であるみたいな感じになったら? 何やってもそれが王道だと言われるとしたら?
編集 (考え込む)
喜多 自分のやりたいことを決める時、色々な前提があるでしょ。王道がいいとか、社会で一般的な価値観に基づいた何かになりたいとか。でもそれって、他者軸なんだよ。自分軸で考えることで、本当にやりたいことが見えてくる。
編集 そうなんですか。
喜多 ほら、東海オンエアの時はめちゃくちゃ熱く語ったじゃん。
編集 いやいや(笑)
喜多 弁護士のところとかはなんか、ボソボソじゃん。明らかにテンションが上がるものって前者だと思うんだよね。趣味ややりたいことのストーリーを洗い出して、何で好きなのかを聞いていくと、自分の指向性や強みが明確になる。
喜多 自分のやりたいことを見極める上でもう一つ言っておきたいのは、「名詞と動名詞」の話だね。
筆者 どういうことでしょうか。
喜多 例えば、朝起きたら記事を編集したり、物語を考えたりするのが嫌いになることってある?
筆者 ないですね。
喜多 それが動名詞。弁護士や、小説家などの名詞は変化するけど、「〇〇すること」っていう興味関心にまつわる動名詞は、変化しない。名詞を信じるな、動名詞を信じろ。
筆者 なるほど。
喜多 そういう動名詞は、幼少期の成功体験や親から褒められたり拒絶されたりっていう経験の蓄積からきている。で、それを誰のために使いたいっていうのは、過去の自分との因縁だったり、近しい人との経験だったりから出てくる。そういう細かいストーリーとか、経験とか全部たくさんあって、自分のやりたいことや価値観が出てくる。
筆者 そういうのってわかるものなんですか?
喜多 自分の過去を一つずつ紐解いていって、根本を知る。それがコーチングの役割の一つ。それに基づいて行動してみたら成功したり、面白いと思えたり。そういう経験をさせてあげるのも役割なんだ。
やっぱり、社会と自分の軸が離れていると怖いけど
編集 今疑問に思ったのは、自分軸がわかっても、他人軸は存在していて、その他人軸自体に自分の幸福ややりがいを感じている人もいるということです。自分軸の趣味や関心が見つかった上でも、やっぱり他人軸に基づいた選択をしたいという人についてはどう思われますか。
喜多 いいポイントだね。やっぱり人には承認欲求や安定志向がある。それは否定しちゃいけない。でも、自分の好きなことでそれを満たせたら最高やんっていうところだよね。むしろ、そうなるためにはどうしたらいいのかを考える方が人生楽しい。でも、それを実現するためには、他の人と違うことをしなくちゃいけないし、リスクもある。時代が追いついてこなきゃいけないこともある。
筆者 時代が追いつく、ですか。
喜多 YouTuberって10年前、どうだった? HIKAKINとか「夢はYouTuberが職業になること」って言ってたんだよ。時代が追いついたよね。
筆者 なるほど。
喜多 俺だって、俺が学生の時に休学するのはめちゃくちゃ怖かったんだよ。
筆者 喜多さんでも怖かったんですか!
喜多 怖いよ。みんな就職してたし。
編集 やっぱり、社会と自分の軸が離れていると怖いですよね。
喜多 でもね、自分がやりたいことって結局、その社会のありようとかを反映してるんだよね。社会課題だったり、世の中こうだったらいいのに、あれが足りてないよね、とか。自分の中の問題意識を形にしていくとそれが次の王道になるんですよ。自分のやりたいことを突き詰めて、社会と向き合う。そっちの方が次の時代を作るし、お金も入ってくる。何より楽しいだろうし、認められる。逆に、既存の枠組みに乗っかっているのは危ういんだよ。
筆者 どういうことですか?
喜多 例えばさ、最近弁護士界隈が作っているのは、AI弁護士だよね。公認会計士や医者もそうだけど、テクノロジーと社会の変化によって、既存の枠組みは崩れていく。昔はね、営業の人が訪問先を間違えないように地図を書く人がいたんだよ。
筆者 今じゃGoogleMapが全て解決してくれますね。
筆者 ただ、今までと同じというのには安心感もありますよね。
喜多 うん。だから、正しく事実を見ましょうねってこと。幅広くアクションして、過去の規範を見直し、時代の先端を知る。すると、自分の熱意と社会のニーズの交差点にやりたい仕事がある。
編集 他者軸と自分軸が交わる。
喜多 そう。自分の軸があって、社会ではこんなことが流行りそうだとわかったら、PDCAをゴリゴリ回して行って、そのさきに辿り着くのが「自分のやりたいこと(仮)」。
筆者 「(仮)」なんですね。
喜多 実践の過程や、時代に沿って変わっていくからね。
[広告]
行きたいコミュニティ、何で行かないの?
筆者 自分のやりたいことをやる上で、コミュニティが大事だと思います。自分に向いているコミュニティはどのように探せば良いのでしょう?
喜多 その発想も、実は面白くて、「何で行かないの?」っていう話なんだよね。興味があったら調べるし、大学生ってこの世で最も自由な身分だし、行けばいいし、話せばいいじゃない。そのためのリサーチ技術もあるし、会ってくれるための肩書き「東大生」っていうのがあるワケじゃん。なんでやってないんだろうね、というところはツッコませていただいて。それ俺の専門だから、結構ガッツリ話しちゃうんだけど、結局、外との関わりを増やすためには、理屈で言えば「自己分析して、自分の興味関心を知って、リサーチをかけて、こういう会社あるんだって調べて、アポをとる。あるいは、その人がいそうなコミュニティや講演会に行って、話しかけるだったり、サークルを調べるとか、すればいいじゃん」って言えちゃう。何が、無理かな。なぜできない?(笑)
筆者 調べる段階にハードルがあると思います。自分の方向性がわかっていないと、その場所に行ってもいいのだろうか、合ってないんじゃないか、と思ってしまう。
喜多 でも、自己分析の本って世の中にたくさんあるじゃん。探せばいいんじゃない?
筆者 恐らく、そこに自己分析が足りてないと気づかない。
喜多 みんな、自分のやりたいことってなんだろうって思ってるよね。「やりたいこと、探し方」ってグーグルで検索すれば出てくるじゃん。
筆者 検索するっていうのは、人に聞くということですよね。それが苦手な人もいると思います。
喜多 そうだね。あとは、自分のやりたいことを見つけたら、既存のルートから外れちゃうんじゃないかと思ってしまったり、いろんなハードルがあるよね。そういうバリアを一つずつ外さないと、その人は動き出さない。
筆者 コーチングの出番ということですね。
喜多 実践的なことを話すと、「言葉を手に入れること」だよね。自分のやりたいことって、世の中では何て言われているんだろうということ。言葉をインストールする。そうすると、人に話した時にポロッと出るんだ。そうすると「それならお前、こういうものがあるよ」って人の縁ができる。するとチャンスが貰えるわけだよ。グーグルで検索する時にも役立つし、授業でも「あ、あの単語が出てきた」ってなる。それで情報や機会が広がっていく。ある程度受動的でも、情報が入ってくるのが東大の素晴らしいところだよね。
筆者 自分の興味関心を言語化することで、アンテナを張る。
喜多 そう、俺が一年生だったときは、「なんか面白い人増やしたいな~」って思ってた。超ざっくりしてるじゃん。でもそれが「ソーシャルキャピタル」や「認知行動科学」っていう言葉になる。「面白い人増やす方法知りたいんです」って言ってたら教授が「それナラティブキャラカウンセリングだよ」って言ってくれたりとか。
編集 言葉のインストールはどこで行えばいいんでしょう?
喜多 万物だよ、万物。言葉や情報なんて無限に転がってるわけじゃん。すごい環境にいるんだぜ、東大って。
コーチングを受ける覚悟は失恋の解消と同じ
筆者 コーチングを受けるには覚悟が必要だというお話を、動画でされていましたが……そうなんですか?
喜多 自分の親からこういう経験を受けて、こういう価値観を得て、こういう問題意識があって……っていう、自分の認知と向き合う覚悟があるか。社会的な要素ではなくて、自分の内面と。
筆者 覚悟、というのはよくわからないです。
喜多 外向きの規範に従えなくなるから、コーチングを受けると。要は、みんなうっすらと自分のやりたいことに気づいてる。「仕事、勉強つまんね~」って言ってる人はやりたいことやってないし、周りに流されている。でもそれは少し気持ちがいいと感じている。考えなくて済むし、失敗されなくて済むし。それは合理的だけど、「あ、やばいかも」と思い始めたら、流れに乗る気持ちよさを捨てて、自分で行動しなくちゃいけない。まぁ怖いじゃん。だからコーチングを受けてやりたいことをあるには、覚悟が必要。
筆者 どうやったら、実感を持ってそれを理解できますかね?
喜多 恋愛に例えてみたら?
筆者 ……友達としての付き合いに安住しているけど、本当は恋愛対象として付き合いたい……みたいな?
喜多 いいね。例えば、東大のミスコン一位の人と付き合ってるとして。周りから「いいなぁ」って言われるし、自分も鼻が高いと思っているけど「なんかこの子合わないんだよなぁ」ってなってる。
筆者 自分の感覚じゃなくて、周囲の感覚に乗って付き合っている、と?
喜多 なんかその、ちょっと地味なA子ちゃんの方が自分に合ってるんだよなって時に、そっちへ振り切る勇気。
筆者 もしそれでA子ちゃんと付き合うことになったら、周りの人から「もったいないぞ」って…
喜多 ひたすら言われるよね。
筆者 伝わってきました(笑)
喜多 (笑う)
筆者 自分の負の部分に向き合う覚悟というのはどういうことでしょう?
喜多 これも、恋愛で例えようか。めっちゃ束縛してくる彼女がいるとする。「メッセすぐ返信して」みたいな。彼氏の方が「それちょっと厳しいから別れる」って言うとするじゃん。女の子はどういう気持ちになる?
筆者 自分にとっては当然の要求なのに、それが拒絶されて、自己嫌悪とか。
編集 自己嫌悪に陥るタイプと、どうして分かってくれないのって相手に迫るタイプもいる。
喜多 そう。さすが解像度高い、女性(笑) そういうことが起こるわけだよね。そこで負の感情が出て、コーチングでは向き合わなくちゃいけない。自分は見捨てられるのが怖いんだ、いつも寂しいんだ、とか。まずこれ、めっちゃ辛そうじゃない? なんで自分は寂しいのか、どうして変わらなくちゃいけないのか、どうして自分を俯瞰してみなくちゃいけないのか。それがめっちゃ大変。自分の感情に基づいた強烈な欲求があって、でもそれじゃあ上手くいかないという現実がある。辛いよね。勉強したいけど、したくないのと同じくらい辛い。
筆者 自分の欲求を分析して、改善しなくちゃいけない……。でもどうやって自分の負の部分に気づくんでしょう?
喜多 スーパー理性が強い人は、自分で分析できるけど、それができなくてもコーチが問いかけてくれる。
筆者 なるほど。
喜多 東大生で「勉強ができない」って言ってる人は大体これで解決します。
筆者 勉強したくない、という負の感情があって……
喜多 具体的に何が嫌で、勉強したくないかを考える。なんでだと思う?
筆者 義務感が嫌な人がいると思います。
喜多 そういう人は、過去にお母さんから義務感で何かをやらされて嫌な経験をしたかもしれない。義務だと分かった瞬間に、嫌だと思っちゃう。僕は細かいところを詰めるのが苦手なんだけど、その理由は僕が小さい時に父親が「お前鈍臭いな」とか罵倒してきたんだよね。そのせいで、細かいことに手をつけようとすると、自分にはできないっていう思い込みが発動しちゃう。
筆者 確かに、そういうところを知るのは辛いですね。
喜多 そこに向き合っていく。
筆者 向き合っていく、とはなんでしょう。分かっていてもできないことってありますよね。
喜多 そこがポイントで、一つ目がその状況を俯瞰的に見ること。二つ目に、その感情を味わう。自分これが悲しかったな、これが辛かったんだなぁとか。自分の感情を体感、体レベルで理解する。すると、次の行動につながっていく。
編集 すごくエネルギーを使いますね。
喜多 その通り、失恋の解消と同じ。
[広告]
コーチングスクール「トランジション・コーチングスクール(TCS)」
編集 我々がインタビューしていたはずが、すっかりコーチングされてしまいました。喜多さんのコーチングスクールに参加する方は、何を目的にしている人が多いのでしょうか?
喜多 主に2パターンですね。1つ目は、本当に人の役に立ちたいという人。リーダーや代表をやっている人に多いよね。どういうことかというと、「最近メンバーに元気がないんです」や「組織がうまくいかないんです」っていう悩みにはコーチングが超効果的。2つ目は、自分を変えたい人。自分が変わることによって、相手に良くしてあげられると直感的に思っている人達。
こちらの動画からコーチングの様子が実感できます。喜多さんの雰囲気や、どういう質問を投げかけているのかに注目!
コーチングについてもっと知りたい、コーチングを受けてみたい。少しでも興味が湧いてきたならば、こちらのリンクから、TCSの公式HPを覗いてみましょう。TCSの概要からネクストアクションまでわかりやすく紹介されています。自分から情報を掴みにいくのが、第一歩ですからね!
終わりに
冒頭のちょっとポエミーな文章(若干恥ずかし)は、取材をした後に取材を受ける前の自分を思い出して書いたものです。”自分の人生に自分で干渉する”という言葉は取材後に思いついたもので、いつの間にか(ひょっとすると中学生くらいから)忘れていたことのように思えます。語学クラスやサークルで、自分はいつも流されてばかり。その活動が自分の真の目的にあっているのかをよく考えていないと、好きで入った大学やサークルも、苦痛になってしまいます。
この記事がきっかけとなり、読者の皆様がコーチングを知り、日々が楽しくなれば幸いです。早速筆者も、明後日にコーチングの予定を入れてみました。自分の羽が自分で動かせるようにね。