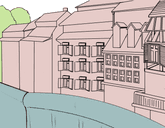「日本独自の文化を創っていこうとするときにこそ、フランス文学研究は役に立つ。」いったいどういうことなんでしょうか。流れるような文体で、フランス文学とその研究の魅力を語ってくださいました。
こんばんは。加藤一輝と申します。フランス文学科の修士課程におります。
- 名前:加藤一輝
- 所属:欧米系文化研究専攻 フランス語フランス文学研究室
フランス文学は語りつくされた?
フランス文学について何か好きなことを書いて欲しいと頼まれ、たいへん光栄なことですが、いざ筆を執ってみると一向に進まず、困ってしまいます。というのも、さいわい本邦では今日までフランス文学研究が盛んに行なわれてきたので、たとえばフランス文学史の概説や、数多くの興味深い作品の訳読註解など、とても豊かな蓄積があって、誰でも気軽に読むことができるからです。ならば、その既に書かれたものを読んでもらえばよいのではないか。あえて付け足すべきことがあるでしょうか?
けれども、このような感覚自体が、もう何世紀も前に指摘されていたことなのです。17世紀の作家、ラ・ブリュイエールは、当時の世相や人間模様を精緻に描いた箴言集『人さまざま、あるいは現代風俗集』を、次のように書き始めています。
「すべては言いつくされた。遅く来すぎたのだ。人間、それも考える人間が存在して、もう7000年以上も経っている。」
実は、こうした感覚は、フランス文学の成立と大いに関わっています。いわゆるフランス・ルネサンス時代の16世紀、キリスト教神学による古典文献研究は形式主義に過ぎて枝葉末節の議論に拘りすぎていると感じていた人文学者(ユマニスト)たちが、自らギリシャ語・ラテン語の原典に当たったとき、そこに全てが書かれているではないか、とうてい自分たちの敵わない優れた作品ばかりではないか、と驚くのです。
内容だけでない、古代ギリシャやローマでは、修辞学(レトリック)が非常に発達している。どういう性質の文章ではどういう用語を使うか、どのような順で話を展開するか、厳密な体系が定まっている。書くということの方法論が確立しているのです。
翻って自分たちの話している言葉はどうか。当時はフランス語といってもラテン語の訛った口語で、北仏と南仏とでは言葉の癖が違い、離れたところから来たひととは話が通じない。もちろん綴字法も定まっていません。これでは鄙語・俗語であって、文藝や思想には適さない、そうしたものはラテン語でなければできない。確かにラテン語は当時の普遍言語というべきものでしたが、それゆえにむしろ、ユマニストたちの拓いた学問の世界は、まだ多くの人々とは切り離されたものだったのです。
[広告]
学問の言語が「広がる」ということ
けれども、そうして古典古代に範を求めつつも、自分たちの言語で文藝や思想を書きたいというひとたちが現われます。たとえば聖書をフランス語に翻訳したルフェーヴル=デタープル、ユマニストとして古典文献研究を進めつつも卑俗で奔放な物語によって社会を風刺した『ガルガンチュアとパンタグリュエル』をフランス語で著したフランソワ・ラブレー、あるいは『フランス語の擁護と顕揚』という宣言のもと詩作を行なった「すばる派」と呼ばれる詩人たちなどです。
これは、当時フランスがイタリア戦争の過程で国民国家としての形を整えつつあったことや、15世紀に発明された活版印刷が実用的な効力を増しつつあったこととも関係しています。
人文科学は、学問ですから普遍性を志向していることは間違いないのですが、その原動力は個別性にあるのであって、こうして普遍言語のラテン語から母語のフランス語へと移行することによって、作者や読者が拡がり、豊穣なフランス文学が生まれることとなったのです。
学問の言語そのものが幾つもある、むしろそのほうがよい、というのは、自然科学と大きく異なる点でしょう。これは人文科学の対象とする人間というものに、普遍的な存在など一人もおらず、各々が個別性を持ちながら全体を構成していることに因ります。
人間の観察眼
16世紀の後半から現われた、キリスト教神学による解釈の定型から自由に人間の本質を探究しようというユマニストの精神を継ぎつつ、それをフランス語で行なった作家たちの系譜を、モラリストと呼びます。
モラルという言葉は、もとは従うべき道徳のことではなく、善し悪しにかかわらず人間の社会的・精神的なありかたのことを指しますので、モラリストというのも人間の理想を語るひとのことではなく、長所も短所も矛盾も含めて人間の総体を観察し記そうとするひとのことです。一般にはモンテーニュ、パスカル、ラ・ロシュフコーなど16~18世紀の作家を指しますが、アラン、ジッド、ヴァレリー、カミュといった現代の作家についてもモラリストと呼ぶことがあります。
しかし、話を繰り返すようですが、モラリストは最初から普遍性を目指しているのではありません。
たとえばモラリストの嚆矢であるモンテーニュには『エセー』という著作がありますが、このエセーという言葉はフランス語の「試み」という動詞から来ています。それは、モンテーニュ自身の生活と判断の試みが記されていることを表わしています。日常において遭遇した出来事、読んだ書物、徒然に浮かんだ考え、そうした他愛ないことについて自分の意見を述べてみる、それを通して自身を明らかにしたものが『エセー』なのです。個別的なものを丹念に描くことが普遍的なものを描くことにもなっている、これが文学の面白いところです。
最初に挙げたラ・ブリュイエールも、そうしたモラリストのひとりです。『人さまざま』という本は、もともと古代ギリシアのテオプラストスというひとが書いた同名の本の仏訳に附して、いまのフランスについて言えばどうか、ということで書かれたものですが、そちらが鋭い人間観察と簡潔な文章とで好評を博し、今に至るまで読み継がれています。
こうした人間観察の態度は、のちに宗教改革を、あるいはフランス革命を惹起し、その精神を継承していることになっている現代フランスにおいても重要な考えかたとなっているのですが、あまり長くなってもいけませんから、この辺で筆を置きましょう。
[広告]
生きる言語としてのフランス文学
さて、これまでの話は、日本でフランス文学を研究するにおいて、類似的に考えることができます。つまり、フランス文学とは第一義的にはフランス語で書かれた文学のことを指すわけですが、しかしフランス文学はフランス語だけのものではなく、それぞれの言語のフランス文学がある、ということです。
先に述べたように、フランス文学には優れた人間観察が多くありますから、これを日本人が読んでも、もちろん違うところもあるでしょうが、頷けるところも多いはずです。そうしたモラリスト文学に魅了されて自分でも「試み」をしてみようという文学者たちは、内容だけでなく文体においても、日本文学を大いに豊かにしました。
あるいはフランス詩、ボードレールやランボーなどの翻訳が日本の近代詩に与えた影響が計り知れないことは言うまでもないでしょう。面白そうなフランス語の作品を探してきて試訳し、その思考法や文体を日本語に取り入れてみる、そうした翻訳もフランス文学研究の醍醐味であり、また重要な役割なのです。もちろんこれはあらゆる異言語文学研究についても言えます。
「文明開化いらいの欧米の物事を紹介するだけで研究者を名乗れるような時代は今や終わったのだ」、と言われて久しいです。
しかし、フランス文学に限って言えば、そうして後ろ盾なく自分で文化を創造しようという状況であれば尚更、フランス文学を研究する意義は増すでしょう。というのも、フランス文学というのは古典古代とりわけラテン語への依存を脱して自律し、独自の価値を広めてゆく過程ですから、では日本ならばどうすべきか、他国の文化を取り入れつつ翻案したり創作したりするにはどうすればよいかを考えるときに、資するところ大であろうからです。
フランス文学研究というのは、実際の研究としては各自が興味を持った作家や作品について扱っています。絶対王政のもとフランス語が純化され爛熟したサロン文化と古典主義演劇が生まれた17世紀、革命と近代化とをもたらす思想が作られた18世紀、多彩な詩や小説によって文学が洗練されていった19世紀、二度の世界大戦と大きな社会変化を経験した20世紀、すでに世紀が変わって16年目になる現在21世紀、興味関心は人それぞれです。
とくに文学科の学生は多かれ少なかれ文学青年ですから、瑞々しい現代文学を味わうのを好みがちで、古い時代の専門を志すひとはあまり多くありません。しかし16世紀フランス文学の持つダイナミズムは、今なお読んで糧となるのではないかと思います。