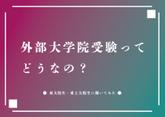
「院試って、実際どんな感じなの?」
「大学院に行きたいけれど、どうやって対策すればいいの?」
「そもそも、自分って院試に向いてる?」
そんな悩みを抱える人も多いのではないでしょうか。
院試をする人口は少なく、彼らが情報発信をすることもあまりありません。
そのため、院試は「未知の世界」と思っている方も多いと思います。
そんな院試の中でも今回は、特に「外部大学院の受験」にフォーカスし、経験者3人に座談会形式でインタビューを行いました。
さらに記事の後半では、3人が所属する「院試の専門オンライン塾」(!?)の塾長に直接取材をしています。
院試についての情報を知りたい、とりわけ外部の院を受験したいという方は是非最後までご覧ください。
外部大学院受験で、あなたの人生が変わるかもしれません。
- お名前:K
- 所属大学/大学院:横浜国立大学➡東大大学院
- お名前:N
- 所属大学/大学院:筑波大学➡東大大学院
- お名前:Y
- 所属大学/大学院:福井大学➡東工大大学院
院試の動機
まず、外部の大学を院試をしようと思った理由を教えてください。
サークルの先輩が、僕の通っていた大学から東大の院に進学されていたんです。その人にあこがれて、進路を選びました。
やりたい研究が学部時代の大学ではできなかったため、外部大学院受験をしました。進学先が国立ということもあり、研究に必要な色々なリソースの充実を感じました。やはり、設備など整っていることが大きいです。
自分も、設備など環境の充実は大きいと思いました。また、自分が東大に受かるのかな、とチャレンジしてみたい気持ちもありました。
院試をするにも、様々な理由があるんですね。
[広告]
院試特有の対策
大学受験までしか知らない大学生が知っておくべき院試の知識などはありますか?
僕の場合、院試は、英語、数学がベースの受験科目でした。それに加え、研究計画書の提出もあったので、そこは大学入試と違うところかもしれません。ただ、面接メインになったり、筆記メインになったり、いろいろあるので、志望研究室を調べてみてください。
研究計画書は、知り合いに添削してもらうのがおすすめです。自分は、幸いにも専門知識を持っている人が周りにいたので、実際に見てもらうことができました。
私の場合は、研究計画書ではなく志望理由書の提出が必要でした。志望理由書と面接の対策は、やったほうがいいと思います。勉強とはまた違った難しさのある部分です。僕は友達や先輩に協力してもらって、志望理由書の添削や模擬面接をしてもらっていました。志望理由書も面接も、書くこと・話すことはだいたい同じ内容なので、まずは志望理由書を練り上げるのが良いのではないでしょうか。志望理由書がしっかり書ければ、それがカンペのようになり、面接で話すことが整理しやすくなると思います。
院試では、研究計画書・志望理由書と、それにもとづく面接ができるかどうかが重要になってくるんですね。
あと、「先生との面談をしないと応募ができない」とオフィシャルに書いてある研究室もあるので、気を付けてください。
え、そんなところがあるんですか?
オフィシャルには書いていなくても、そういうところは多いです。ただ、東大は研究室訪問に行かなくても、意外と突破できます。むしろ、地方国立の方が、行かないといけない場合が多いと思います。
あくまでも大学院によって違いますし、自分の行きたい専攻によっても大きく異なりますが、院試は内部生にやさしい感じです。逆に外部生には厳しい戦いになります。そもそもの情報が少ないので。ただ、専攻によるので、勝ちやすい場所を見極めるのが大事になってきます。
一人で臨むのでなく、先輩などに協力してもらうことが大事なんですね。
いつごろ院試準備をはじめた?
院試の準備をはじめたのはいつごろですか?
3年生の12月ごろです。4年生になるあたりから、本格的に勉強をし始めました。
研究室も、実際に訪問してみて、とても満足できる環境だったのでモチベーションが上がりました。
ただ、そのころちょうど、コロナでどこにも行けなくなってしまったんですよね。5〜6月ごろに、zoomでようやく面談ができたイメージです。
院試を意識したのは、福井大学に入学してからすぐでした。他の方よりも、かなり早めだと思います。
本格的に対策を始めたのは、3年生の夏休みです。3年生の5月に院試説明会に参加し、12月に現地の研究室を訪問して、コンタクトを取り始めました。現地訪問とzoom合わせてトータルで6~7ほどの研究室を訪問しました。
私は、学部生のときは普通に就活をしてました。就活を終えて、大学4年生になってから院試を始めました。
院試準備のタイミングは、人それぞれなんですね。
[広告]
具体的な院試の勉強スケジュール
院試対策ではどんな勉強をしましたか?
過去問の分析から始めました。院試は、出てくる範囲が決まっているんですよ。まずは、過去問の分析から始めるのが定石です。
そこから、専門的な知識の勉強を始めました。大事だと思ったのは、今と合格レベルのギャップを把握して、逆算した努力をすることです。
院試勉強の時間をいかにして捻出するのかということはとても重要です。1日10時間は勉強していました。そこに時間が取られてしまったので、大きな声では言えませんが、当時の研究室での研究はほどよく力を抜いて取り組んでいました。笑
自分も、最初に過去問を見るのは本当に大事だと思います。今の段階でどれだけ解けるかを把握しないと、院試合格までの道のり(全体像)が分からないので。院試は、正しいベクトルで正しい努力をしたら、必ず受かるものだと思ってます。まずは正しい方向をしっかり知っておくのが重要です。
具体的には、まず過去問を解いて傾向と実力把握、その後は過去問解答作成と教科書で基礎復習を往復して、完成度を高めました。一通り終わったら、市販の院試の問題集でひたすら数をこなしました。院試の筆記試験対策では、量をこなすのが大事だと感じます。
院試の辛いところは、過去問の回答がないことです。その点、市販の問題集は、すべてに回答がついています。東大の過去問はメルカリに出てたりしますが、東大以外は過去問の回答の入手難易度が上がります。過去問自体は、だいたい各専攻のHPでダウンロードするか、郵送で取り寄せるか。あとは現地で手書きでコピーです。HPは最新5年とかしかないことが多いので、古いものは研究室の先輩経由でもらうことになります。
え、思った以上にアナログというか、地道に過去問を集めるんですね。
院試は大学受験と違って、赤本がないんです。先ほどのお話にありましたが、回答がある、といっても、だれかが作成した回答があるだけです。先輩が作ったものなので、間違っていることもあります。
院試は、大学受験より、大学の定期試験の対策に似ています。人脈を活用するところとか、まさにそうですよね。
院試は情報戦だと思います。当時は知り合いに、外部の大学を受ける人がいなかったんです。そこで、院試をする人が集まるサークルをなんとか見つけて、情報を取りに行きました。ESCAPEというサークルで、いろいろ情報を受け取ることができました。
自分は大学4年になってから院試対策を始めました。数学が得意だったので、数学の比重が高いところを受けました。こういった、戦略的に突破できるところも院試の良いところだと思います。
時間的には、1日で多い時には10時間程度。平均で6時間は勉強しました。
決まった勉強手順があるというよりも、志望先に合わせた情報収集がカギになってくるんですね。
受験生へのメッセージ
最後に、院試を控えている受験生へのメッセージをお願いします!
何かしらの目標を持つのが大事です。ひとそれぞれ価値観は違うので、その目標を達成するための手段としての院試をしたほうがいいと思います。人生における目標を持って、そのための手段として院試を使ってください。そのほうが、モチベも出て、合格確率は高まります。
自分の場合は院試を突破して、レベルの高い環境に身を置けることに喜びを感じました。また、刺激が得られて、人脈が広がりました。自分がこんなところにいてもいいのかと思うくらい、恵まれた環境です。
外部の大学院を受ける動機は、人それぞれです。自分の場合は、以下の3つのメリットが得られました。
1 自分の目標をもって、全力を尽くしてチャレンジする経験ができた
2 まわりに流されないで、自分の意志で将来を選ぶ経験ができた
3 環境が大きく変わる経験ができた
環境によって、その人の器は変わると思ってます。ずっと同じ友達とつるむのもいいですが、勇気を出して新しい環境に身を置くと成長につながると思います。自分の場合は、この選択をして良かったと思います。
自分は大学時代、やりたいことができない環境で4年間過ごしました。学部受験の結果が満足いかないものになった方の中には、やりたいことをできないでいる人も多いのではないでしょうか。そんな方が、人生変えるきっかけになるのが院試だと思います。
どんなにささいなことでも良いので、自分が一番の何かを持っていることが自信になります。東大に行って日本一の学歴を手に入れることでもいいと思いますし、特定分野の知識でもいいと思います。院試は、自信が手に入るまたとない機会です。みなさん、いろんな分野を学んでいると思うので、その分野を極められる環境を手に入れるための院試でもいいと思います。負けず嫌いな人、ぼんやりと自分に自信が欲しい人は、自信をもつきっかけとして院試を使えます。
院試をそんなふうに考えたことはありませんでした。でも、研究室単位で、自分の得意分野を活かした場所を選べるので、自分の強みを活かしてナンバーワンを目指すには、たしかに絶好の機会ですね。
それ以外の面でもメリットはあります。先輩の就職活動を見ても、大学院で外部受験をすると、就活で圧倒的に有利になるんです。今後の人生の幅が広がります。
院試って、頑張ればだれでも挑戦できるんです。自分は大学受験で、センター国語の点数が200満点中60点台でした。しかし、大学生の時に頑張ったおかげで、院で逆転できました。自分に自信をもって、人生の幅を広げるための敗者復活戦として、最大のチャンスである院試を活用してください。
おお、大学受験で思ったような結果が出なかった人に届けたいメッセージですね。
[広告]
オンライン院試塾「esma」について
最後に、今回インタビューをさせていただいた方たちが講師を務めている、オンライン塾「esma」について、塾長にインタビューをさせていただきました!
なぜ、院試の塾を作ったんですか?
座談会の内容でもわかるように、院試はかなり閉鎖的な世界です。
情報がかなり不足していて、先輩達からの知見を後輩に受け継ぐ仕組みが十分にできていないんですよね。この不透明な現状に不満を抱いている大学生も多いと思いました。本当に研究に興味があって学力があるような人が、情報収集を間違ったばかりに院試に落ちてしまうのは、とてももったいないですよね。
たしかに、初耳の情報がとても多かったです。
また、院試を通じて人生の可能性を広げるという選択肢を、もっと多くの大学生が持ってもいいのではないかと思いました。人生における目標を達成するための一つの選択肢として、院試対策を提供する塾を作りたいと思ったのが、塾をつくった動機です。
他の院試向けの塾とはどこが違うんですか?
講師の質と、講師とのやり取りの密度が違います。
講義で得られるものは、どうしても講師の力量によってきますよね。自分の達成したい目標をすでに達成した人に教わることがどんなことでも大事です。なので、院試の指導経験のある人に講師になってもらうなど、徹底的に講師のクオリティを高めてます。
おお、すごいこだわりです。
また、講師と生徒の間でのやりとりの密度にも注意を払っています。生徒が学習をしようとする上で、現状に対するフィードバックがよりパーソナライズした形で返ってくる必要があると考えています。
今の時代はインターネットが発達していますが、インターネットが解決できない悩みが二つあります。
どんな悩みでしょうか?
一つ目は、現状に欠けているものだけを的確に与える能力。例えば、「院試 勉強法」と調べても、院試の一般的な共通項である勉強法は出てくるかもしれませんが、所詮はそれまでなんですよね。自分の最大効率ではありません。多くの人の最大公約数です。
二つ目はインターネットにない情報を得ることです。これは当たり前のことなのですが、インターネットに出てくる情報は誰かが書いたものです。院試をする人は、母数自体が少ないですし、必然的に発信者の数も限られてきます。すると、リアルな情報がなかなか出てきにくいんですよね。
確かに。
現場の世の中の情報システムで解決できない悩みを、解決するのがうちの塾です。逆説的ですが、情報が氾濫している現代において、最も効率的な方法は少人数での密度の濃い講義だと思いました。カリキュラムの作成においても、院試経験者が院試時代に抱いた悩みと、その解決策を泥臭く集め、徹底的にリアルな院試の現状を踏まえた講座にしています。「こんな講座があの頃欲しかった」と、運営陣一同が思うような講座になったのは、それだけ現状の『院試』に対する課題感がみんなあったからかもしれません。
実際の体験から、後輩に同じ苦労をさせないようにと講座を作成していったんですね。最後に、院試を考えている大学生へのメッセージをお願いします!
院試は人生を変えるための手段です。対策のために無駄な時間を使ったり、ストレスを感じるのは、人生全体を充実させる上でマイナスだと思います。最大効率で勉強を進めて、 大学生活全般を充実させたい、ひいてはその後の人生の選択肢を増やしたい、と思う方は是非一度、オンライン塾esmaの説明会に来ていただければと思います。
ありがとうございます!
最後に
院試をしたことがない身としては、初めて知ることがとても多く、新鮮な時間になりました。それだけ世の中に情報が出回っていないということも同時に実感しました。
オンライン塾「esma」の院試講座は、以下のリンクからアクセスできます。 院試を考えている方は、見てみてください!
最後まで記事を読んでくださった皆さんに感謝申し上げます。








