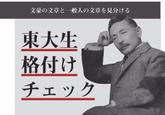
みなさん明けましておめでとうございます。
UmeeTライターのチロルです。
2021年も何卒よろしくお願いします。
正月といえば、テレビ朝日のテレビ番組「芸能人格付けチェック」が恒例になっていますよね。番組では「一流芸能人」が、様々なジャンルの「本物」と「偽物」を見分けています。
番組を観て、僕は考えました。
「一流」の東大生ならば、「一流芸能人」がしているのと同じように、勉学における「本物」と「偽物」を見分けることができるはずだと。
ということで、年明け早々5人の「一流東大生」に集まっていただきました。
今回はこの5人に、「文豪の書いた文章」と「わたくしチロルが書いた文章」を見分けてもらいます。
集まっていただいたのは、こちらの5人。
- お名前:せきりりこ
- 所属:2年。文科三類。文学部国文学科に進学予定。
- 備考:企画に参加する直前に「吾輩は猫である」を読んでおり、準備は万端である。
- お名前:ひでちゃん
- 所属:1年。文科一類。
- 備考:論説を中心に本をよく読んでいる。所属する学生団体で文章を書く機会も多い。
- お名前:いわたけい
- 所属:3年。文学部現代文芸論専修。
- 備考:俳壇で最も権威のある新人賞とされる「角川俳句賞」を最年少受賞した本物の俳人。過去には俳句甲子園で最優秀賞を獲得してもいる。今企画の注目株。
- お名前:ゆうな
- 所属:2年。理科二類。教育学部教育心理学コースに進学予定。
- 備考:普段はビジネス書がメインで文学はあまり読まないと謙遜しているが、UmeeT編集部で大活躍している敏腕ライターなので期待大でしょう。
- お名前:わかな
- 職業:1年。文科一類。
- 備考:UmeeT編集部。普段は全く本を読まないが、初売りで3万円擦ってきたのでとりあえず気分は良好。
「一流東大生」なら、文豪の文章と素人の文章など、当然見分けられるでしょう。
それでは「東大生格付けチェック」開幕です!
第1問
第1問は、東京大学を舞台にしていることでも有名な小説、夏目漱石の「三四郎」。
今回は、東大本郷キャンパスにある三四郎池(この作品が由来でこう呼ばれている)で、主人公の三四郎がのちに思いを抱くことになる美禰子と初めて出会うシーンを抜き出しました。
A
ふと目を上げると、左手の丘の上に女が二人立っている。女のすぐ下が池で、向こう側が高い崖の木立で、その後がはでな赤煉瓦のゴシック風の建築である。そうして落ちかかった日が、すべての向こうから横に光をとおしてくる。女はこの夕日に向いて立っていた。三四郎のしゃがんでいる低い陰から見ると丘の上はたいへん明るい。女の一人はまぼしいとみえて、団扇を額のところにかざしている。顔はよくわからない。けれども着物の色、帯の色はあざやかにわかった。白い足袋の色も目についた。鼻緒の色はとにかく草履をはいていることもわかった。もう一人はまっしろである。これは団扇もなにも持っていない。ただ額に少し皺を寄せて、向こう岸からおいかぶさりそうに、高く池の面に枝を伸ばした古木の奥をながめていた。団扇を持った女は少し前へ出ている。白いほうは一足土堤の縁からさがっている。三四郎が見ると、二人の姿が筋かいに見える。
B
荘厳なゴティックの建物群を抜けて木立に入る。木々は池を囲むように生えており、どことなく西洋の森にいるような心持ちになった。見下ろすと、池の対岸を上った位置に女が二人立っている。一人の女はあでやかな次縹の衣装を羽織り、髪は島田である。三四郎のいる窪みからは距離およそ百尺といったところで、その相貌を知ることはできない。女は夕日に向かって立っている。けれども日の光はゆらゆらと池に反射して、女の全身を隈なく浮かび上がらせていた。右の手に握られた団扇が白く映えている。どうもその手をもう一人に向け、顔を覆っているように見えた。三四郎はもう一人の真白が看護婦だと思った。次縹の女は真白の女の少し後ろに立っている。三四郎は二人の挙動をしばしじっと見つめていたが、女は共に反対の木立をただ眺めているのみで、水ぎわのようすを気にする様子がない。一向に池越しで三四郎はやや低い位置の二人を眺めた。
みなさんも、どちらが文豪の文章か是非考えてみてください。
ではみなさん一斉に文豪の文章だと思う方を選んでください。
せーのっ!
…
…
…
…
うわ……
まさかのいわたけいさんが1人だけBという結果になりました。
いわたけいさんは、どうしてBを選びましたか?
これAの方は、頑張って考えないと位置関係が分かりにくかったんですよね。
池の位置関係が分かってから、女の様子が自然に頭に入るという流れが取れているのがBでした。
あと、「島田」とか当時の用語が入っているのでBかなと。
Aを選んだみなさんも理由を聞かせてください。
僕は逆に、分かりにくいからこそAが夏目漱石なんじゃないかと思ったんですよね。
あと、Aの方はパソコンで打っちゃうと変換されてしまうような箇所もひらがなになっていて、それもAを選ぶ要因になりました。
私も同じですね。分かりにくいからこそ、昔の人の文章なんじゃないかと。
私もひらがなが多いのが気になりました。
チートっぽいこと言っちゃうと、最近「三四郎」読んだんですよね。
……⁉︎
なんとなく最初の方の文章に見覚えがありました。
あと、他の作品でもそうなんですけど、夏目漱石って、文章のリズムがずっと独り言を言っているみたいな感じなんですよ。Aの方は、その場でだんだん目線を動かしているのが分かるので、夏目漱石っぽいと思いました。
さあ、決定打っぽい発言が出ましたがまだ分かりません。記憶違いということも考えられるので。
それでは正解を発表します。
文豪が書いた文章は……
…
…
…
…
Aです!
イエーイ!!
(ショックを受けている)
1番の注目株だった岩田さんが初戦から外し、大混戦の予感です。
[広告]
第2問
続いては、中島敦の「文字禍」です。
非常に短い作品ながら、中島敦の代表作の1つとなっています。今回は主人公が「文字の霊」の存在を確信した場面を抜き出します。
A
しばし、ナブ・アヘ・エリバは不可思議な体験をした。文字を眺めているうちに、いつの間にやそれらが無意な断片の集合体へと散逸していったのである。意味のない線分が集まった所で、いかに音と意味を生み出すことができるのか、どうにも分からない。博士は驚歎した。一体今までの常識がその一番深い底から丸ごと引っ繰り返ってしまった様で、視界がぐにゃりと翻った心持になる。無意の集合が有意になる境界へと考えを巡らせるうちに、博士は文字の霊の存在を確信した。手・脚等、身体の部分部分の集合体が、魂の統制によって人間になるというのなら、同じく線分の集合が文字たるのは、一つの霊によるものだと判断するのが道理だろう。
B
その中に、おかしな事が起った。一つの文字を長く見詰めている中に、いつしかその文字が解体して、意味の無い一つ一つの線の交錯としか見えなくなって来る。単なる線の集りが、なぜ、そういう音とそういう意味とを有つことが出来るのか、どうしても解らなくなって来る。老儒ナブ・アヘ・エリバは、生れて初めてこの不思議な事実を発見して、驚いた。今まで七十年の間当然と思って看過していたことが、決して当然でも必然でもない。彼は眼から鱗の落ちた思がした。単なるバラバラの線に、一定の音と一定の意味とを有たせるものは、何か?ここまで思い到った時、老博士は躊躇なく、文字の霊の存在を認めた。魂によって統べられない手・脚・頭・爪・腹等が、人間ではないように、一つの霊がこれを統べるのでなくて、どうして単なる線の集合が、音と意味とを有つことが出来ようか。
ではみなさん一斉に文豪の文章だと思う方を選んでください。
せーのっ!
…
…
…
…
みなさんBですね。
理由を聞かせてください。
中島敦って漢文的な表現を多用する人だと思うんですけど、Bの文章の最後の「〜でなくて〜出来ようか」って、とても漢文らしいじゃないですか。そこで中島敦の雰囲気が出ていると感じました。
中島敦の文章って、漢文的だけど実は漢語が多いわけではなくて、漢語自体は今の文章の方が多い印象なんです。Aの方が漢語自体は多かったので、今の人が書いた文章なんだろうと感じました。
「有つ」と「老儒」が、中島敦っぽいなあと。
あと、Bは無意味な句点が多かったんですよね。それが冗長になっている気がして。必ずしも今の人が読みやすい文章が文豪の文章なわけではないという1問目の反省があるので、読みにくいBを選びました。
みなさん物凄い分析力ですね。
いやまだAが答えって決まったわけじゃないんですけど。
私は文章の違いはよく分からなかったんですけど、「?」があったから、Bを選びました。本家が使ってないのに「?」をチロルさんが使うのは難しいかなーと思って。
うーん、Bの方がなんとなく好きかなーと。
なんか編集部は理由が雑ですね。
それでは結果発表です。
文豪の文章は……
…
…
…
…
Bです!
30分くらいかけて考えたのに、誰も引っ掛からなくてちょっと落ち込みました。
第3問
次は芥川龍之介の「鼻」。
非常に大きな鼻を持つ僧が登場する太宰の代表作の1つです。今回はその冒頭部を抜き出しました。
A
禅智内供の鼻と云えば、池の尾で知らない者はない。長さは五六寸あって上唇の上から顋の下まで下っている。形は元も先も同じように太い。云わば細長い腸詰めのような物が、ぶらりと顔のまん中からぶら下っているのである。
B
池の尾の禅智は、五六寸の鼻を持つ内供である。その鼻は尾端まで丸々太く、腸詰のような形貌をしている。あまりに強烈なつくりをした鼻のために、池の尾中で禅智内供のことを知らぬものはおらぬのである。
ではみなさん一斉に文豪の文章だと思う方を選んでください。
せーのっ!
…
…
…
…
うわああああ
まだ結果はわからないから落ち込まないで。
Aを選んだみなさん、理由を聞かせてください。
これタイトルが鼻ですけど、Bの文章は鼻というより大きな鼻を持つ禅智内供の説明なんですよね。タイトルから考えて、鼻にフォーカスした方が本家だろうと。
Bの文章だと、そのあとに鼻の話は続かないですよね。Aの方がこれから発展しそうに感じました。
あと、「ぶら下がっている」という表現が印象に残っているので、本家かなと。
私これ知ってます。読んだのは多分中1くらいなんですけど、覚えてます。
僕もなんか読んだことあるなあって気がしたんですよね。
冒頭ってやっぱり印象に残りやすくて、「禅智内供」の4文字から始まる感じとか、「唇」をわざわざ「上唇」と言っている感じとかが、見覚えあるように思います。
「鼻」、みんなめっちゃ読んでますね。
Bを選んだゆうなさんはどうですか?
私もう全然分からないので、またチロルさんの心理あてクイズをしてるんですけど。
ゲームの趣旨変えないで
「知らぬものはおらぬ」っていう表現が可愛すぎる気がしたので、わざわざそんな表現をチロルさんが使うか?と思い、Bを選びました。
それでは結果発表です。
文豪の文章は……
…
…
…
…
Aです!
僕の文章が可愛いことが分かりました。
[広告]
第4問
続いては中原中也の「北の海」。
初めての詩の問題ですね。
A
海にいるのは、
あれは人魚ではないのです。
海にいるのは、
あれは、浪ばかり。
曇った北海の空の下、
浪はところどころ歯をむいて、
空を呪っているのです。
いつはてるとも知れない呪い。
海にいるのは、
あれは人魚ではないのです。
海にいるのは、
あれは、浪ばかり。
B
やがて見えなくなるのは、
宵月明かりの水面です。
淋しい心は、
光ばかり捨てて……
純潔を願うこころが
空の貧しさを呪う頃、
鈍色の岩肌が、
風をうけています。
やがて見えなくなるのは、
宵月明かりの水面です。
淋しい心は、
光ばかり捨てて……
ではみなさん一斉に文豪の文章だと思う方を選んでください。
せーのっ!
…
…
…
…
マジか……
せきりりこさんはどうしてBを選びましたか?
Aの詩がめっちゃ可愛かったので「これはチロルさんなのでは…?」と思いました。
あと、光を捨てていくというのが、比喩として高度で、なかなか思いつかないんじゃないかなと。
でも誰もBを選んだ人がいないので、すごく不安ですね。
Aを選んだみなさんも、理由を聞かせてください。
詩は間違えたくないんですよね……笑
これ、第1連と第3連が共通していて第2連が違うというのは、どちらも同じ構造ですよね。
Aの方では、第2連の呪う主体は浪です。
一方でBの方は、呪いの主体が作者の心になってます。
Bの詩からは、Aの詩が先にあったうえで、それを「呪い」という要素だけ保存したまま作り替えようとした結果、呪いの主体が別のものに移ってしまったというような「ズレ」を感じました。
この短い詩から主体のズレまで読み込んでくるとは……
「呪い」がこの詩の重要な要素だと感じていて。Bだと呪いへの言及があっさりしすぎている気がして、体言止めで呪いを強調しているAが本家なんじゃないかと思います。
あとBだと宵月夜だから、「北の海」というより「秋の海」という感じですよね。Aは冬の寂しい感じもあるので「北の海」っぽいなと。
内容だと私はあんまり分かんないので、「……」とか使うのはチロルさんっぽいかなと思って、Aを選びました。
それでは結果発表です。
文豪の文章は……
…
…
…
…
Aです!
ちなみに言っておくと、「……」は中也も多用してますよ。
代表作の「汚れつちまつた悲しみに」も「……」で終わります。
第5問
いよいよ最終問題です。
最後は文豪の代表ともいうべき太宰治の「女生徒」。
少女の一人称視点で進行する太宰には珍しいタイプの小説です。
A
「みんなを愛したい」と涙が出そうなくらい思いました。じっと空を見ていると、だんだん空が変ってゆくのです。だんだん青味がかってゆくのです。ただ、溜息ばかりで、裸になってしまいたくなりました。それから、いまほど木の葉や草が透明に、美しく見えたこともありません。そっと草に、さわってみました。
美しく生きたいと思います。
B
私は「すべての人」を愛さなければいけないと決心しました。可笑しいでしょう。思いを巡らす中に、空のようすも変りました。青がしだいに、よりいっそう青になっていきました。息をするのさえ苦しいので、いっそ服をまるごと脱いでしまいたいのです。それでも草木がとても美しく見えたのです。
私は清らかに生きたい。
ではみなさん一斉に文豪の文章だと思う方を選んでください。
せーのっ!
…
…
…
…
またか……
まだわかりませんからね。
まずはAを選んだみなさんから理由を聞かせてください。
これは一番迷いました。でもなんとなくAの方が読んでいて気持ち良かったので、Aにしました。Bの「思いを巡らす中に、空のようすも変りました」という文章も、Aの「だんだん空が変ってゆくのです」を解説したもののように思えました。
太宰はずっと敬体で続く印象があったので、最後の文章になんとなく違和感があって、Aにしましたね。
私も最後の文章が気になって、Aの方が文豪っぽいオーラが出ている気がしました。
最後の1行は、有名な文章なんですよね。確か「美しく」だったような気がするので、Aかなと。でもこれ間違ったら嫌だなー。「女生徒」好きなので。
Bを選んだせきりりこさんはどうですか?
Aの最後に「そっと草に、さわってみました。」という文章があるじゃないですか。この文章いるか?と思って、Bにしました。
太宰は「走れメロス」しか読んだことないんですよ……でも「そっと草にさわるか……?」という違和感があったので。
それでは結果発表です。
文豪の文章は……
…
…
…
…
Aです!
序盤に好調だったせきりりこさんがラスト2問で不正解となり、、まさかの(本家流にいえば)「二流東大生」になってしまうという結果に終わりました。
[広告]
終わりに
まずは全問正解の「一流東大生」2人に、感想をお聞きします。
本は読まないけど国語は得意だったので、その意地を見せれて良かったです。(ドヤッ)
1番最初の「三四郎」の文章が僕の中では難しかったですね。よくこれ作ったなと、制作者側の立場になって考えたりしてました。
続いて、4問正解した「普通東大生」の2人。
問題がうまいなあと思って。
僕、大学1年生のとき、同クラとたまに「たほいや」っていうゲームを遊んでたんですよ。辞書から選んだ分からない単語について、辞書の本来の説明文と出題者が作った偽の説明文を混ぜて、正しい方を当てるというものなんですけど、みんなうまいんですよね。問題を作るのも当てるのも。
……もうちょっと勉強します。スノビッシュな間違え方をしてしまったのがちょっと恥ずかしいですね。
私の戦略がチロルさんの心理を当てるというものだったんですけど、それでも4問正解できたので、UmeeT愛は示せたかなと思います。
的確な解説をしながら正解していく人がカッコ良かったです。
最後に、「二流東大生」のせきりりこさん。
最初正解できたので調子乗りましたね……結論から言うと、私はチロルさんの文章が好きだったということだと思います。
わあ。
読んでない作品は本当に分からないなあと思ったので、文学部らしく、しおらしく読書しようと思います。
参加してくれた5人のみなさん、そして「6人目の一流東大生」として、最後まで記事をお読みくださったみなさん、ありがとうございました。
いかがだったでしょうか?最後まで全問正解することはできましたか?
全問正解できなかったあなたは、「一流東大生」を目指して文豪の作品を読んでみてはいかがでしょうか?
一応今回の作品が無料で読める青空文庫のリンクも貼っておきますね。




















