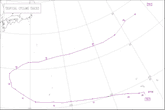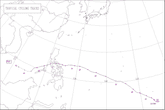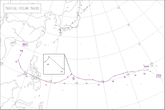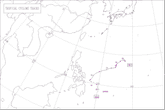台風はニューイヤーカウントダウンの夢を見るか?
年が明けた。1/1 0:00:00を過ぎたら会う人会う人に「あけましておめでとう」と挨拶するわけだが、どうせなら何か珍しいものに対して新年の挨拶を言ってみたい。できるだけ大きいものがいい。
富士山やスカイツリーは大きくて申し分ないが、どうせなら何かレアなものがいい。大きくて、比較的短い寿命があって、冬に出会うのが稀なもの。
よし、台風にしよう。
相手と時差があると面倒なので、対象は日本と近いタイムゾーンに限定して。南半球ではお正月は夏にあたって台風は珍しくないので、北半球限定で。
まとめると、こういうことになる。
観測史上、日本標準時1月1日0時0分0秒に日本近海に存在し、日本列島と一緒に年を越した台風は存在するのか?
[広告]
調べてみた
そもそもの台風の定義は下のとおり。
北西太平洋に存在する熱帯低気圧のうち、低気圧域内の最大風速がおよそ17m/s(34ノット、風力8)以上のもの。 [1]
西太平洋の熱帯低気圧がこの定義を満たした状態になることを「台風が発生した」と表現し、その後勢力を弱めて風速が基準を下回った時点で「台風」という呼び方をしなくなる。この二つの時刻の間で1/1 00:00:00を迎えた、つまり年をまたいだものがあるか、1951年以降の日本付近の台風のデータベースをもとに調べてみた。[2]
結果、5つの台風が年を越していたことがわかった。
●1952年台風27号”HESTER” 発生1952年12月28日 消滅1953年1月5日
図の紫色のラインが台風の経路を描き、数字が日付を表している。ちなみに台風には番号のほかに人名が与えられ、140個で1サイクルの名前を発生した順番につけていく。
●1959年23号”HARRIET” 発生1959年12月24日 消滅1960年1月2日
こちらはなんと、12月24日に発生し「あけましておめでとう」だけでなく「メリークリスマス」までしてしまった台風。年越しはフィリピン上空で迎えた模様。ちなみにフィリピンの公用語、タガログ語での新年の挨拶は “Manigong bagong taon.(マニゴン・バゴン・タオン)”
●1977年台風21号”MARY” 発生1977年12月21日 消滅1978年1月2日
こちらも「メリークリスマス」した台風。クリスマスは太平洋のマーシャル諸島近海で過ごした模様。ちなみにマーシャル諸島の住民にはキリスト教のプロテスタントが多く、メリークリスマスと挨拶したら暖かく迎え入れられていたかもしれない。
●1986年台風29号”NORRIS” 発生1929年12月23日 消滅1987年1月2日
息が長く、経度で50度以上西に進んだ。
●2000年台風23号”SOULIK” 発生2000年12月30日 消滅2001年1月4日
こちらは年だけでなく、20世紀から21世紀へ、世紀までまたいでしまった台風。縁起がいいのか悪いのか微妙だがこういう変わり者もいる。
つまり、こういうことになる。
1951年以降、だいたい10年に1回のペースで台風が年を越しているが、2000年末を最後に21世紀に入ってからはそのような例はまだない。
さらに上の5例を見てわかるように、データ上で年を越す台風が日本に上陸したことはなく、実際に強風にさらされながら「あけましておめでとう」を言える可能性はかなり低い。
筆者は理学部の地球惑星物理学科[3]に所属しているのだけれど、夏の熱帯気象についての卒業研究の合間に思いついたムダ知識のような調べ物でもやっているうちに興が乗ってしまうのが気象を研究する面白さの一つ。
気象衛星をはじめとする観測システムやスーパーコンピュータを使ったシミュレーションの技術向上によって膨大な量のデータが日々蓄積されていく。
そのなかから稀に「光るもの」が見つかることがあり、どの時間・空間スケールで、どの物理量に目をつけるか次第で未解明の現象の理解に少しずつ近づくことができる。
今もこれを書きながら「夏の台風と冬の台風って根本的な違いが何かあるものなんだろうか?あるとしたらそのそれらは一年のなかでいつごろ切り替わるんだろう?」と思ってデータを漁ってみたくなってきたところ。
[1]気象庁予報用語 http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/haichi2.html
[2]デジタル台風 http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/
[3]東京大学理学部地球惑星物理学科 http://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/epphys/index.html